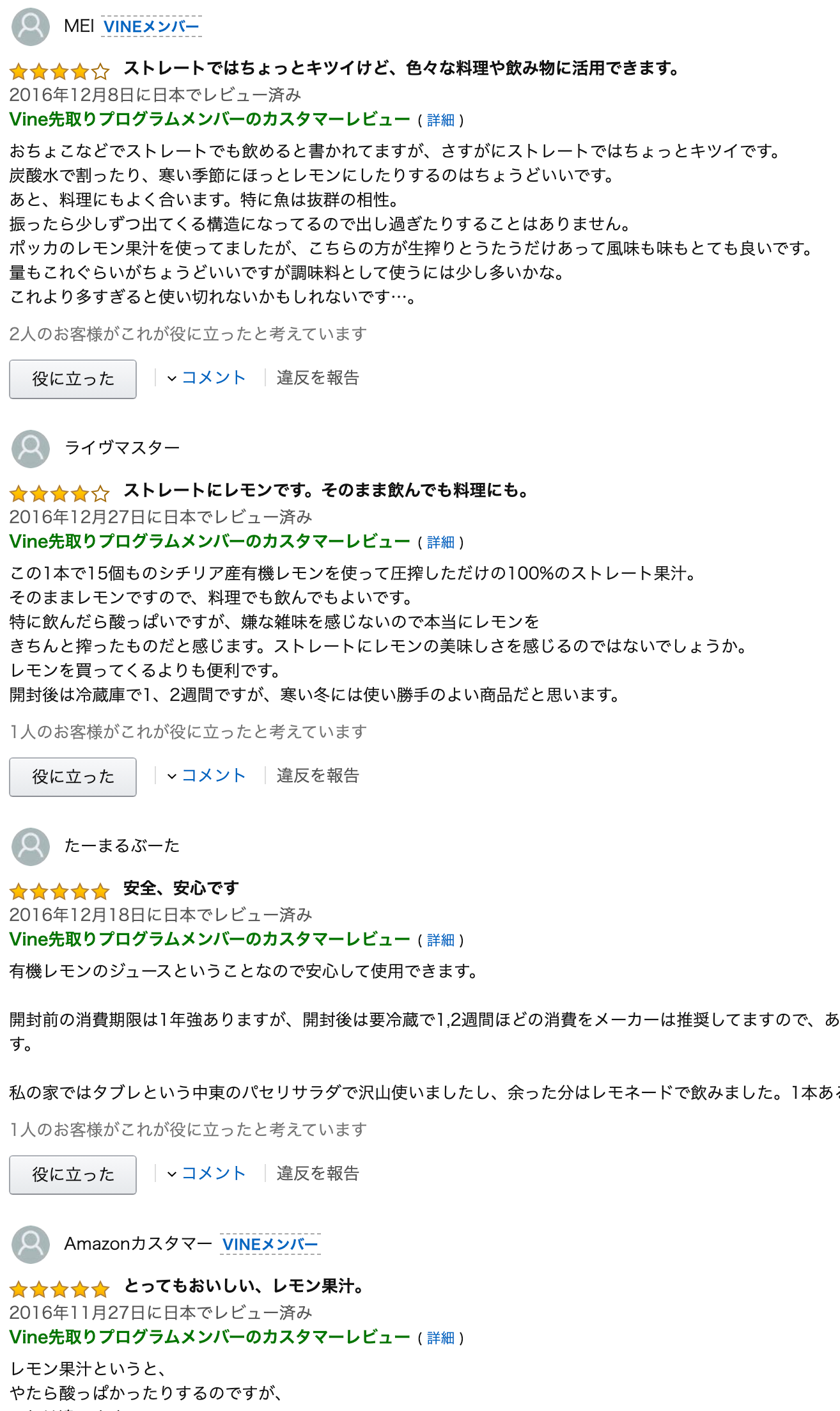鈴木 祐
SBクリエイティブ
売り上げランキング: 1,556
SBクリエイティブ
売り上げランキング: 1,556
鈴木祐氏は、メンタリストDaiGoのブレーンとして有名な人である。昨年の論文誤読問題でちょっと株が下がった感があるが、有能なサイエンスライターであることに間違いはない。
鈴木祐氏は単著もあるのだが、先日購入した『ヤバい集中力』(鈴木祐著、SBクリエイティブ刊)をとてもためになるなあと思いつつ、パラパラめくっていて、ふと以下の点が目に止まった。体を動かすことが脳に対する休憩になるということで、「アクティブレスト」について解説したくだりだ。
たとえば学生を対象にした実験では、最大心拍数の約30%という負荷で10分の運動を行っただけでも被験者の脳機能が改善し、認知テストの結果では集中力と記憶力に有意な向上が見られています。(P237、初版第2刷)参照元として挙げられているのは「Rapid stimulation of human dentate gyrus function with acute mild exercise」という論文だ。有名な論文らしく、タイトルで検索するとAbstractが読める。
ここを読んでまず「?」と思ったのは、「最大心拍数の約30%という負荷」の部分だ。ワシはバリバリの中年オヤジなので、普段は60〜80くらい、先日熱を出して120に心拍が上がると不安になってくる。たとえば、階段を駆け上がって150になったら、結構死にそうな感じになりそうだ。最大心拍数が150として約30%だと45しかない。45を普段の心拍に足すのだろうか。そこの計算がよくわからない。で、元の文献をちょっと探してみることにした。
この本の末尾には、参考文献がたくさん挙げてあって、著者が多くの文献を参考にしてこの本を書いたのだろうと思えた。それはいいのだけど、なぜか文献ページの紙が濃いグレーで、文字がやや読みづらい。文献ページが色付きになっている本は、学術書ではあまりないと思う。ここも「?」と感じた点。
さらに、文献ページのスペースの使い方があり得ないほどバラついている。寝ていないとダメな数字が立っている箇所が1つあるのはご愛敬としても、スペースのバラつきは編集者が見落とすのは考えにくい。もしかすると、編集者はここを読んでいないのかもしれない。まあ、読者もほとんど読まないページなのは確かだが。
閑話休題。本題の「最大心拍数の約30%」だが、該当部分をAbstractを引用しておこう。
A single 10-min bout of very light-intensity exercise (30%V˙O2peak) results in rapid enhancement in pattern separation and an increase in functional connectivity between hippocampal DG/CA3 and cortical regions (i.e., parahippocampal, angular, and fusiform gyri).問題の「V˙O2peak」(正しくは、Vの上にピリオドが来る)だが、日本語訳は「最高酸素摂取量」になるらしい。解説をちょっと調べた限りでは、心拍数と何の関係もないとは言えず、多少は関係あるようだが、「V˙O2peak」は少なくとも心拍数の単位ではない。「最大心拍数の約30%の負荷」ではなく、「最高酸素摂取量の30%程度しか酸素を取り込まないでいい程度の負荷」という意味になりそうだ。
医学・生理学はまったく素人なので、正しい解釈をしているかどうかは正直わからないが、鈴木祐氏の解釈は不正確である可能性が高いと思った。